こんにちは!トッティです!
「投資ってタイミングが難しそう…」「高い時に買って損をしたらどうしよう…」そんな不安を抱える方にこそ知ってほしいのが「ドルコスト平均法」という投資手法です。特に、これから長期的に資産形成をしていきたいと考えている方にとっては、非常に心強い法則です。私自身もNISAやりたての学生時代から実施しました!今回は、投資初心者でも実践できる「ドルコスト平均法」について、わかりやすく解説していきます。
ドルコスト平均法とは

ドルコスト平均法(英:Dollar-Cost Averaging)とは、一定の金額を定期的に投資していく方法です。たとえば、毎月1万円ずつ投資信託を購入するなど、「株価に関係なく、同じ金額で買い続ける」のがポイントです。価格が高い時には少ない量を、価格が低い時には多くの量を買うことになり、結果として平均を狙うことが出来る効果があります。例として、毎月1日に1万円を好きな銘柄に投資しようと決めて、一時的に株価が上がったり下がったりしても途中で売却はせずにコツコツと積み立てるといって形です。これを聞いた方の中には「株ってパソコンに張り付いて売買するものじゃないの?」「平均を狙うのなんて可能なの?」と思うと思います。以下にドルコスト平均法を知っておくべき理由を記載しました。
長期投資をやる上でドルコスト平均法を知っておくべき理由

購入タイミングを考えるストレスが減る
相場の上下に一喜一憂せず、機械的に投資を続けられるので、精神的な負担が少なくなります。
リスク分散になる
一度に大きな金額を投資するよりも、時間を分散して投資することで、価格変動のリスクを軽減できます。
習慣化しやすく継続しやすい
自分の所得の範囲内で毎月一定額を積み立てることで、無理なく続けることができます。まさに、長期的な資産形成に向いている手法です。
税金や手数料がかかりにくい
ドルコスト平均法は「コツコツ積み立てて長期保有する」ことが前提の手法なので、頻繁な売買を行わない=その都度かかる売買手数料や、売却益に対する税金が発生しにくいというメリットがあります。
ドルコスト平均法の効果が通用しない、または効果が薄い場合

ドルコスト平均法は「長期的に成長が見込まれる資産」に対して有効な手法ですが、すべてのケースで効果を発揮するわけではありません。以下のような場合は注意が必要です。
- 長期的な利益が予想できない銘柄に投資する場合
- 価格がずっと横ばい、もしくは右肩下がりの銘柄
- 短期売買を前提とした投資スタイルの場合
これらのデメリットも頭の中に入れていただけると良いです。
NISAでは、どのように設定するのか

ドルコスト平均法をNISAで活用するには、「つみたて投資枠」の活用がおすすめです。つみたて投資枠では、金融庁が認めた長期・分散・積立に適した投資信託の中から商品を選び、毎月自動的に一定額を積み立てる設定ができます。
設定方法の流れは以下の通りです:
1. 証券口座でNISA口座を開設(すでに開設済みの方はスキップ)
2. つみたて投資枠を選択
3. ドルコスト平均法に合った投資信託を選ぶ(インデックスファンドが人気)
4. 毎月の積立金額と引き落とし日を設定
5. 長期で積み立てるだけでOK!
証券会社によっては、ボーナス月の増額設定や毎週積み立てなど、柔軟な積立スケジュールも選べます。積み立て投資枠の銘柄は仲介業者が取引をするため、最初に設定してしまえばあとは自動的に積立が続くため、忙しい人にもぴったりです。
まとめ : 無理のない範囲で継続すること
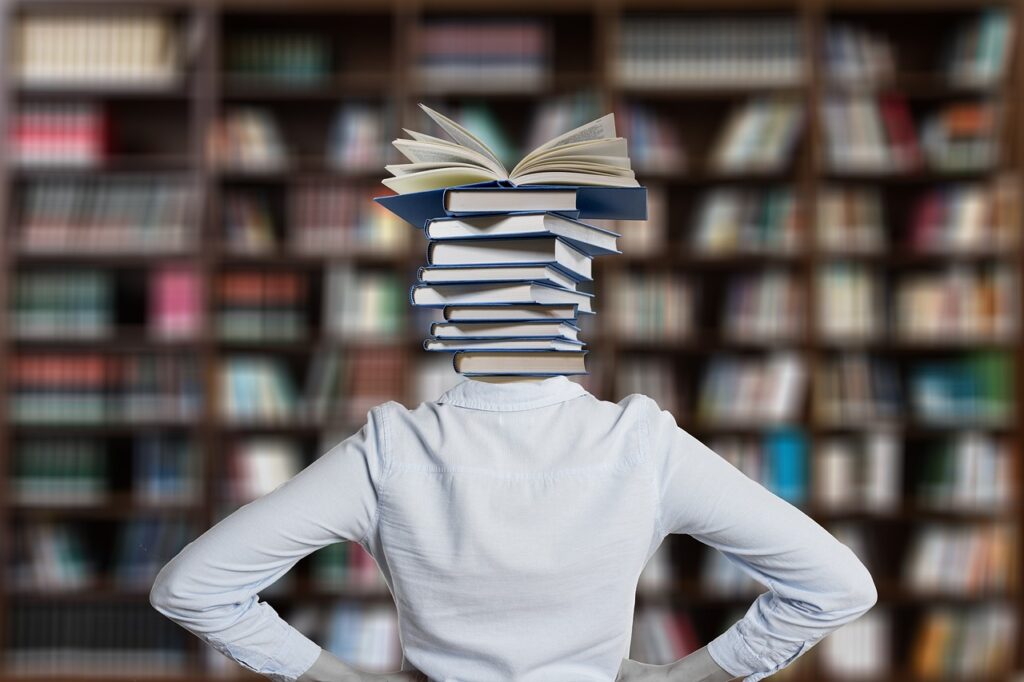
ドルコスト平均法は、投資のタイミングに悩まされることなく、長期的にコツコツ資産を増やしていきたい人にぴったりの方法です。「相場の波に乗る」のではなく、「波の中で淡々と積み上げる」。これが、着実な資産形成につながる考え方です。私はこの考え方をNISAを始める段階から知っていたため不安が少なく現在まで続けることが出来ております。これから長期投資を始める方は、ぜひドルコスト平均法を取り入れて、無理のない投資習慣を身につけてみてください。
今後もこのようなFPや自身の体験談に関することを勉強しつつ発進していこうと考えております。「これは間違っているだろ!」と思われた方はご指摘していただけると嬉しいです。
最後まで見ていただきありがとうございました!ブログ以外では、インスタグラムやX(旧ツイッター)などでも活動をしております!興味がある方はぜひ見てくださると嬉しいです!



コメント